第6回 「 認知行動療法」
何年か前から認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)を学び始めました。もともとAaron. T. Beck先生が始めた治療法で、うつ病、不安症、強迫症、心的外傷後ストレス症、統合失調症、不眠症等々、多くの疾患に用いられ、効果が実証されています。私自身はこれまで3人のうつ病の患者さんにCBTを実施し、皆さんご自分の希望する場所に戻る、あるいは進むことができ、良かったと思います。
治療が始まる前、患者さんは異口同音に「自分の考え方を正されるのではと心配だった」と仰っていました。「あなたの考え方のせいで病気になった」と言われると思っておられたようです。しかし治療が終わる頃、ある方は「考え方を正すのではなく、全体を俯瞰して見ることが大事なのですね」と仰っていました。まさしくその通りで、CBTでは、事実を見落として考え方が偏ってしまった結果、気分が落ち込んでしまうのではないだろうか、という仮説を治療者と一緒に検討します。バランスよく事実を見つめ直すことが重要なのです。
また、CBTでは「行動」にも注目します。治療の最初の頃、患者さんの多くは気分が落ち込んで意欲がわかず、身体もだるくて不活発な状態になっています。そのようなうつ状態の中でも、自分が好きな行動、好きだけど最近遠ざかっている行動をリストアップし、生活の中で実際に取り入れてみることをお勧めします。しかしながら、ほぼ全員の患者さんは「今は無理なので、気分が良くなってから、いずれやってみます」と仰います。私たち治療者は「行動することで気分が上がる」ということを説明しますが、最初は信じてもらえません。さらに「1日は誰にとっても24時間なので、好きなことをして気分が改善すれば、その分、嫌な気分で過ごす時間が減りますよね。どんな些細な事でも良いので、まずは取り組んでみましょう。」と繰り返し勧め、どうやったら取り組めるか一緒に計画を練ります。大切なことは、「やってみたら気分が少し晴れて過ごしやすい時間が増えた(=嫌な気分の時間が減った)」、「変わらないと思っていた嫌な気分が少し軽くなった」など、自分の経験・実験をもとに、行動が気分を変えてくれるということに気付いていただくことです。それだけで随分お元気になる方もおられます。認知は体験と結びついたときに初めて本当の意味で変化します。このように認知行動療法では、試しに行動してみる➡認知が変化する➡その変化により行動もまた変化する➡さらに認知が変わってゆく・・・を繰り返しながら、その人らしい生活を築くお手伝いをさせていただきます。
行動することで気分が変わって過ごしやすくなるという治療技法を行動活性化と言います。認知行動療法にはこのほかにも生活や人生の困りごとに対処するコツが沢山あります。
せっかく学んでいるので、それを今後皆さんにもご紹介したいと思います。
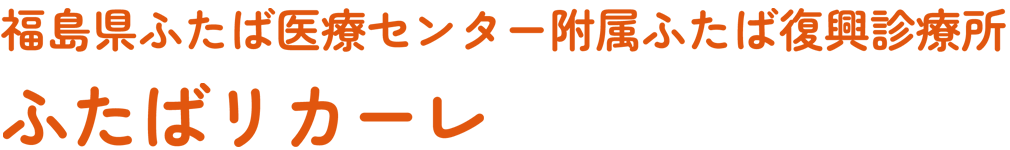
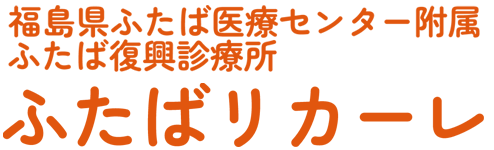
 文字サイズ
文字サイズ